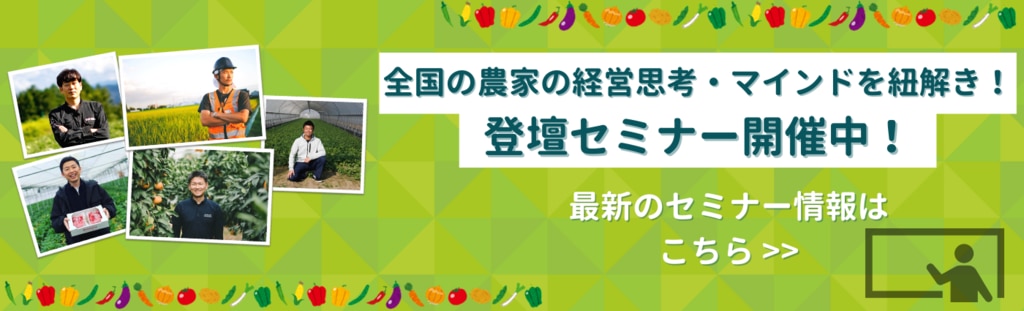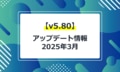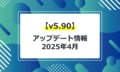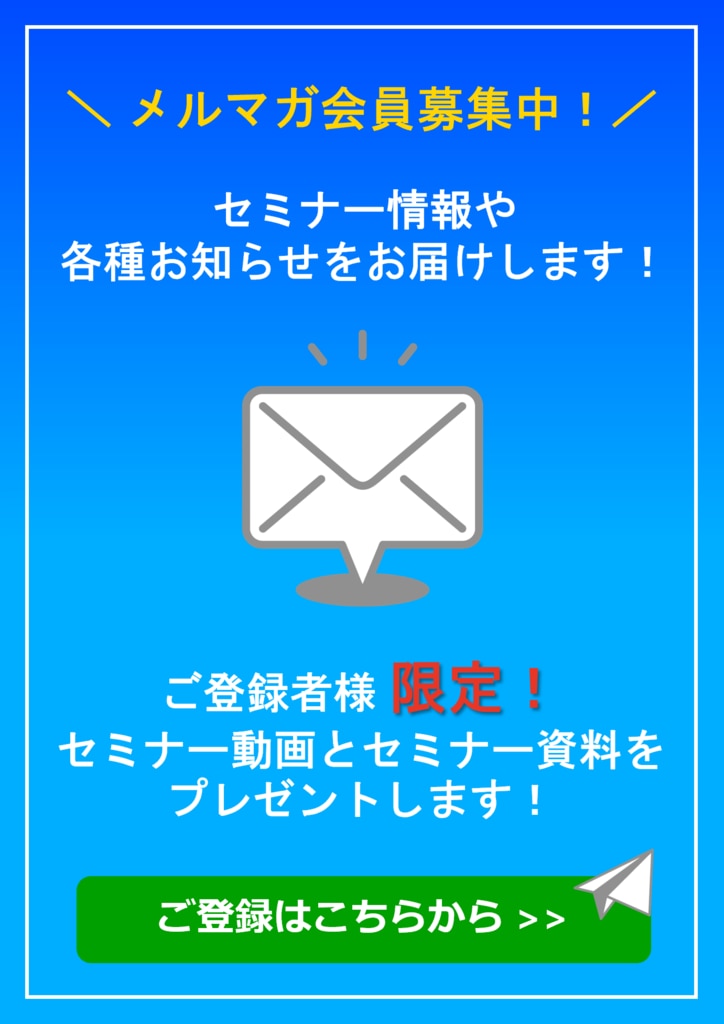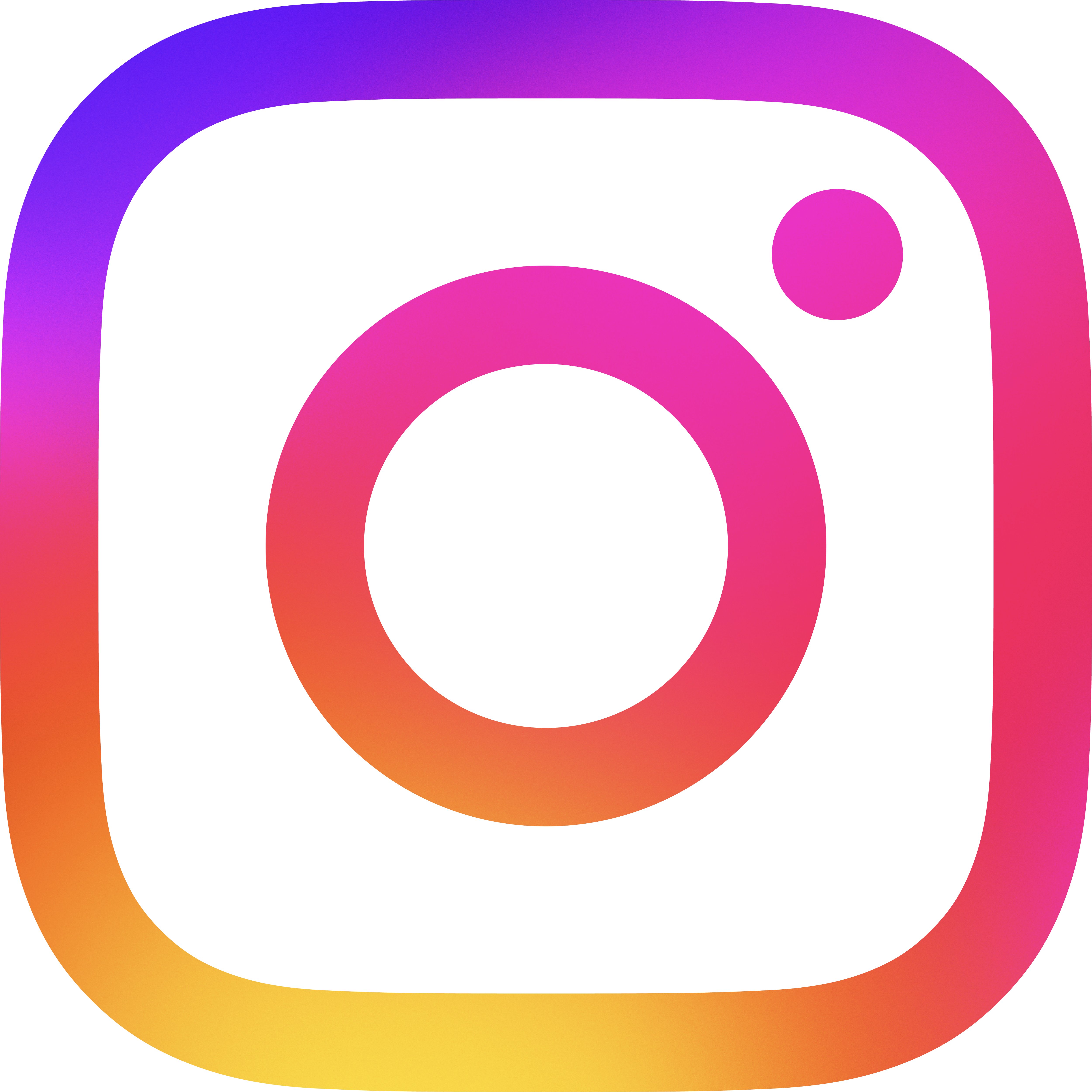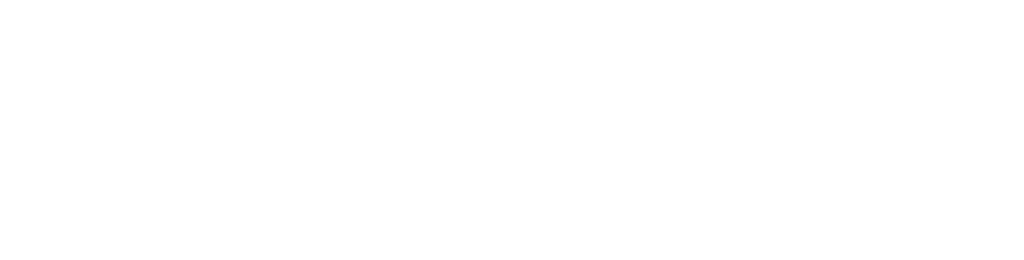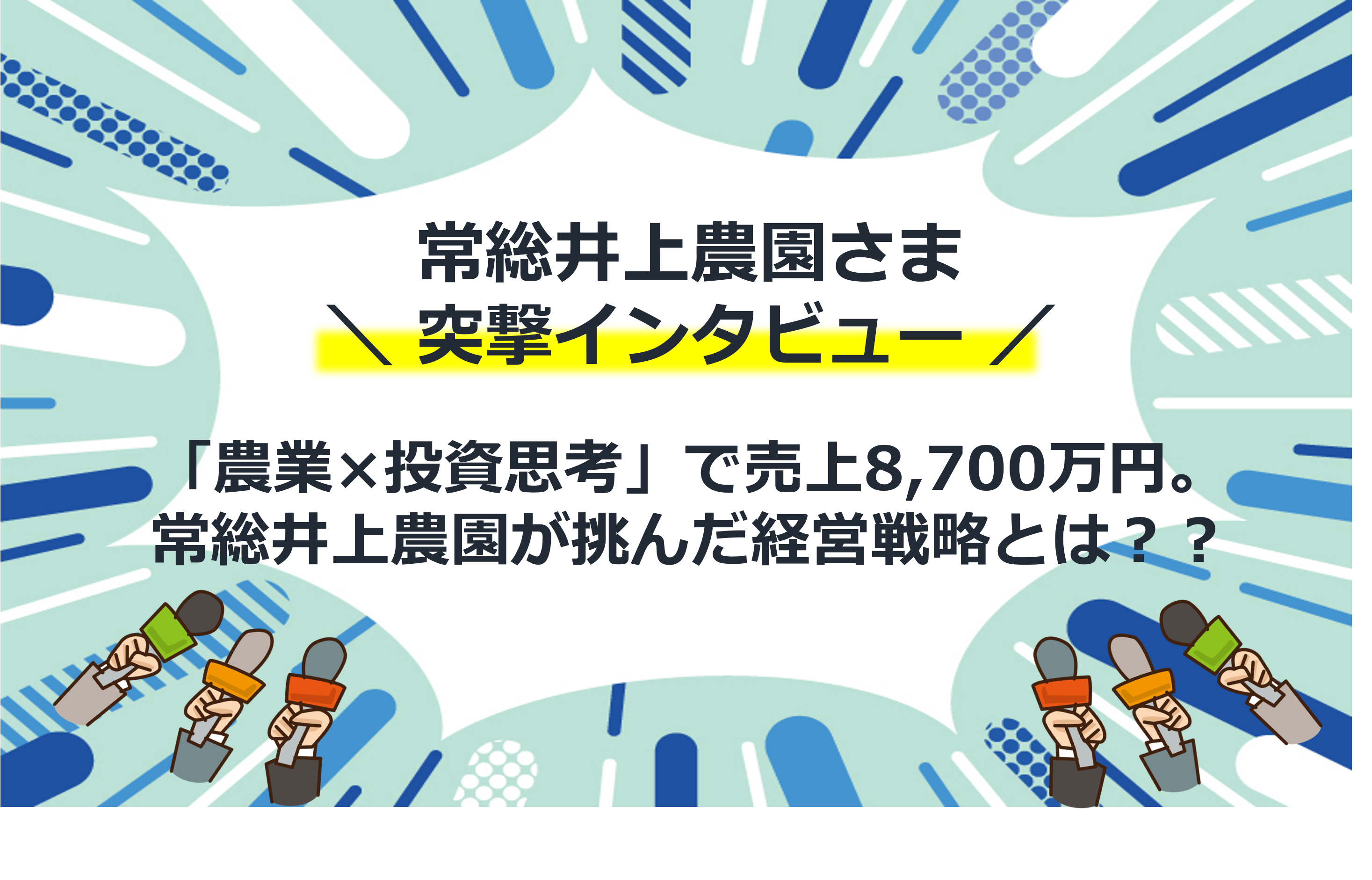
常総井上農園さま突撃インタビュー
「農業×投資思考」で売上8,700万円。
常総井上農園が挑んだ経営戦略とは??
2011年に就農し、2019年に事業承継された常総井上農園。
代表の井上真晴さんは、実家の農家を継ぎながら事業を拡大し、白菜・キャベツ・ネギの「定量安定供給」を可能にする独自の強みを武器に、農業の枠を越えた取り組みを展開しています。
「常識にとらわれずに様々なことにチャレンジしていきたい」そんな井上さんの言葉の背景には、常総市という土地の利を活かした戦略と、小さなPDCAを丁寧に回しながら挑戦を積み重ねる経営スタイルがありました。
目次[非表示]
Q1.就農のきっかけを教えてください。
A.きっかけは、将来設計ワークの“本音”発言。
私は3人兄弟の長男として生まれましたが、もともと末の弟が農業を継ぐ予定でした。ただ、自分自身のキャリアと実家の将来を冷静に考えたとき、「長男である自分が継ぐのが最も合理的だ」と判断し、事業承継を考えていました。
転機となったのは、前職(アウトドア専門店)での将来設計ワークです。社員の前で「いずれ農業をやるつもりです」と発表したところ、社長に思いっきり叱られました(笑)
その時は“ぶっちゃけ過ぎたとは思いましたが、あの瞬間に、自分が本当に進みたい方向を言語化できたのだと思います。勢いもありましたが、それ以上に、将来的なことを考えて農業を選んだというのが実感としてあります。2011年3月8日に実家へ戻り、就農しました。

Q2.就農当時に印象に残ったことを教えてください。
A.震災をきっかけに”契約出荷”に重きを置くようになった。
就農したわずか数日後に東日本大震災が発生しました。震災直後、茨城県では市場出荷している農産物の風評被害が広がる中、契約出荷分においては大きな影響を受けていない状況を知りました。そこで”契約”という側面での顧客開拓に注目し自社商品ならではの強みをうたえるよう、当時では珍しいGAP認証を取得しました。その後はJA契約部会を離れ、自ら販路を切り開く経営へと舵を切りました。その時は何よりも妻の後押しが心強かったですね。
Q3.井上さんのベースとなっている考え方を教えてください。
A.「変化」と「投資」。
私のベースとなるのは「常に変化したい」という思いで、周囲からは「井上は楽しんでいる」と映るようです(笑)。一言で表すなら「変化を楽しむ投資家目線の農業経営」ですね。伸び代を得るには失敗が必要だと思っているのですが、無計画に失敗を重ねるのではなく、リスクにも持ちこたえられるような余裕を持った上での経験を積めるようにしています。投資に対する独自の視点を養ってきたことで、農業の本質的な価値や業界の動きを多角的に捉える力が培われたように思います。
捉え方や業界によってはプラスにもマイナスにも捉えられるため、どこに自分の立ち位置を持っていったら面白いか、利益に繋がるかを常に考え続けています。
Q4.売上を突破した際に工夫したことを教えてください。
A.売上6,000万→8,700万円へ。農業+αで顧客の課題解決を考えた。
部会に所属していた頃の売上は約6,000万円でしたが、部会を抜けた現在は8,700万円まで伸び、自社トラックを活用することで手数料を削減し、販売提案の自由度もアップしました。

その中での大きな変化点は「双方のメリットを意識したアイデアの掛け合わせ」の発想です。配送ルートに合わせて使用済みコンテナの回収を行ったり、顧客が処理に困っていた食品残渣を配送便の復路に積む形で引き取り、畑の堆肥に再活用したりと、農業以外の付加価値で相手の困りごとを解決できるよう考え提案してきました。
「相手にとってのメリット」を常に考える姿勢を意識しています。目の前の利益よりも、信頼関係を築き、長くお付き合いいただけることの方が最終的に大きな利益に繋がると考えているからです。常に「相手が本当に困っていることは何か?」に意識を向けながら、提案・行動をしています。
常総市ならではの地の利を活かした経営戦略として、工夫しながら小さくPDCAを回してきたからこその売上増だったのだと思います。
Q5.大量出荷、安定供給が強みとなっている理由とは?
A.「自社便×冷蔵対応」で、さらなる安定供給へ。
フレキシブルな対応が付加価値となり、お客様から契約をいただいていると感じています。というのも、部会に入っていたときの経験を通して産地の特徴、スケジュール感、現場の声が感覚的に分かっていたため、他の地域からの出荷量が少ない際に常総井上農園から出荷するなど、市場のニーズを汲み取って柔軟に対応してきました。
さらに、業界ならではの“あるある”や現場のリアルな状況を把握するため、業界内の人と日頃から積極的にコミュニケーションを取り、現場の声を拾い続けてきました。相手に“ぶっこんで聞く”くらいの姿勢で、ニーズの本質を探っています。設備面では、鉄コンテナの導入や冷蔵トラックへの投資により、温度管理を徹底し、納品時の品質を担保。結果、量・質・スピードのすべてを満たす供給体制が整いました。
また、「良い農産物をつくるだけでは足りない」と考え、補助金の活用・求人広告・行政イベント参加など、知ってもらうためにも力を入れています。選ばれる農家であるために、“届ける力”と“見つけてもらう工夫”を両立してきたことが、現在の契約につながっていると感じています。
Q6.従業員のモチベーションを高めるために取り組んでいることを教えてください。
A.人が辞めない組織づくりも、経営の柱。
お金や資格といった点から投資を惜しまないということが大事だと思います。
私たちの強みは、なかなか人が辞めない点です。現在は日本人従業員が1名と、外国人技能実習生を5人雇用して、そのうちの1人をリーダーに任命しています。彼は、常総井上農園での勤務年数も長く、これまでの姿勢や信頼関係から自然と周囲を引っ張る存在になっていたことが、リーダーとしての抜擢につながりました。

彼は母国のインドネシアで事業を立ち上げてコロナ禍で戻ってきた方なのですが、私としては彼にずっと働いてもらいたいくらい信頼をおいています。そのため、そういった方々には評価として賞与を「夏」と「冬」に年2回支給するなど、優秀な人材にはお金や資格といった投資を惜しみません。
Q7.クロスエイジはどんな存在ですか?
A.常総井上農園にとっての盲点に気づかせてくれる存在。
2023年12月からクロスエイジの支援を受ける中で、農業界の外にある“常識”を知り、視野が広がりました。ビジョンや組織設計にも新たな光が差し込んでいます。
Q8.今後のビジョンを教えてください。
A .目指すのは「人が人を呼ぶ農園」。関わる皆さんに喜んでいただけたら嬉しい。
私自身が現場に出なくても仕事が回っていく、そして人が人を呼ぶ農園を目指していきたいです。関わるお客様や従業員の皆さんが「常総井上農園で良かった」と喜んでいただけるよう、これからも尽力してまいります。ひとまず、売上1億円の達成が目標です。その土台は揃ったので、あともう少しのところまできています。
「変化」と「投資」を恐れず、課題に立ち向かい続ける井上さん。
経営をする上では売上や利益といった数字と向き合うことはシビアであり、時として経営者を悩ませますが、井上さんの“農業経営者”としての柔軟さと、“投資家”ならではの洞察力と行動力を兼ね備えた視点はまさにこれからの一次産業のヒントでしょう。大変に勉強になるインタビューでした。
井上さん、ありがとうございました。
(執筆:柴萌子/編集:ひのりほ)