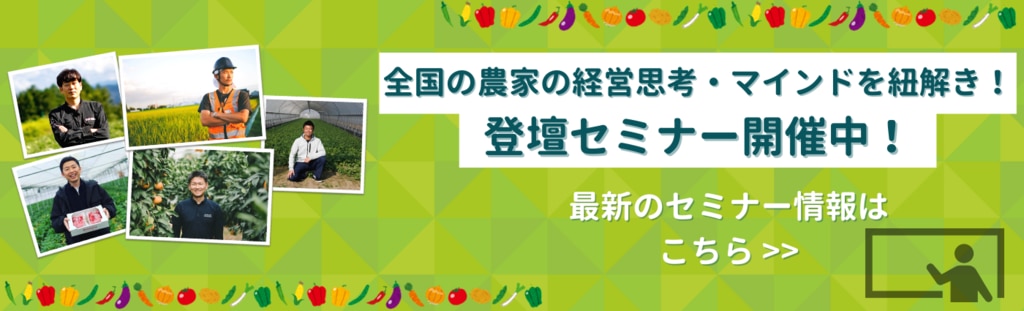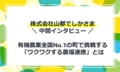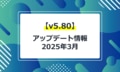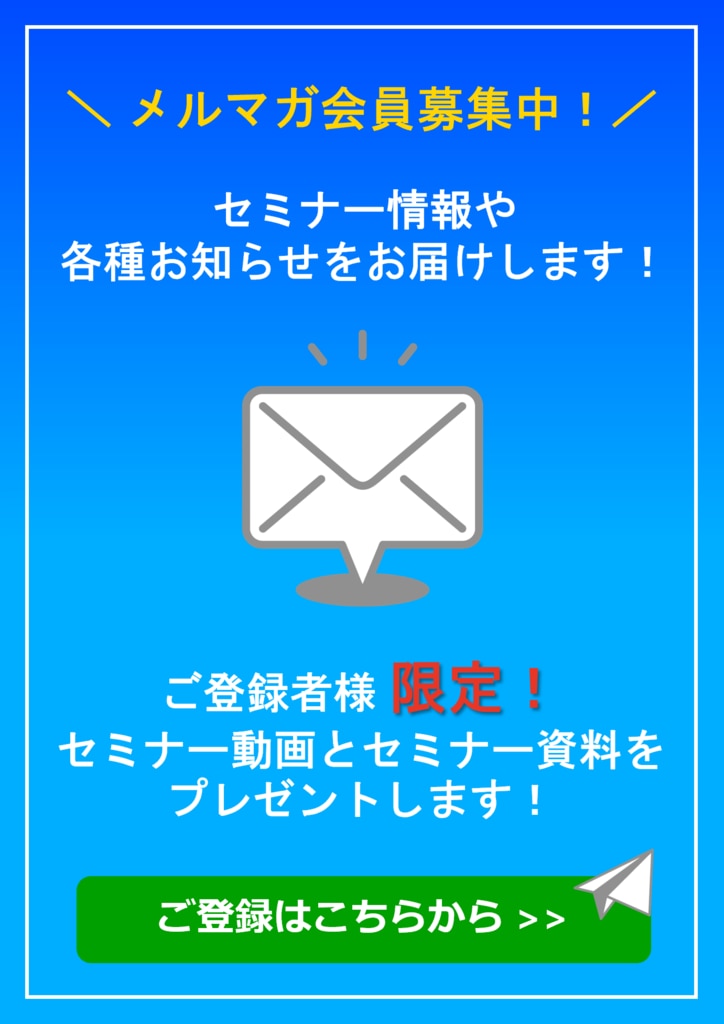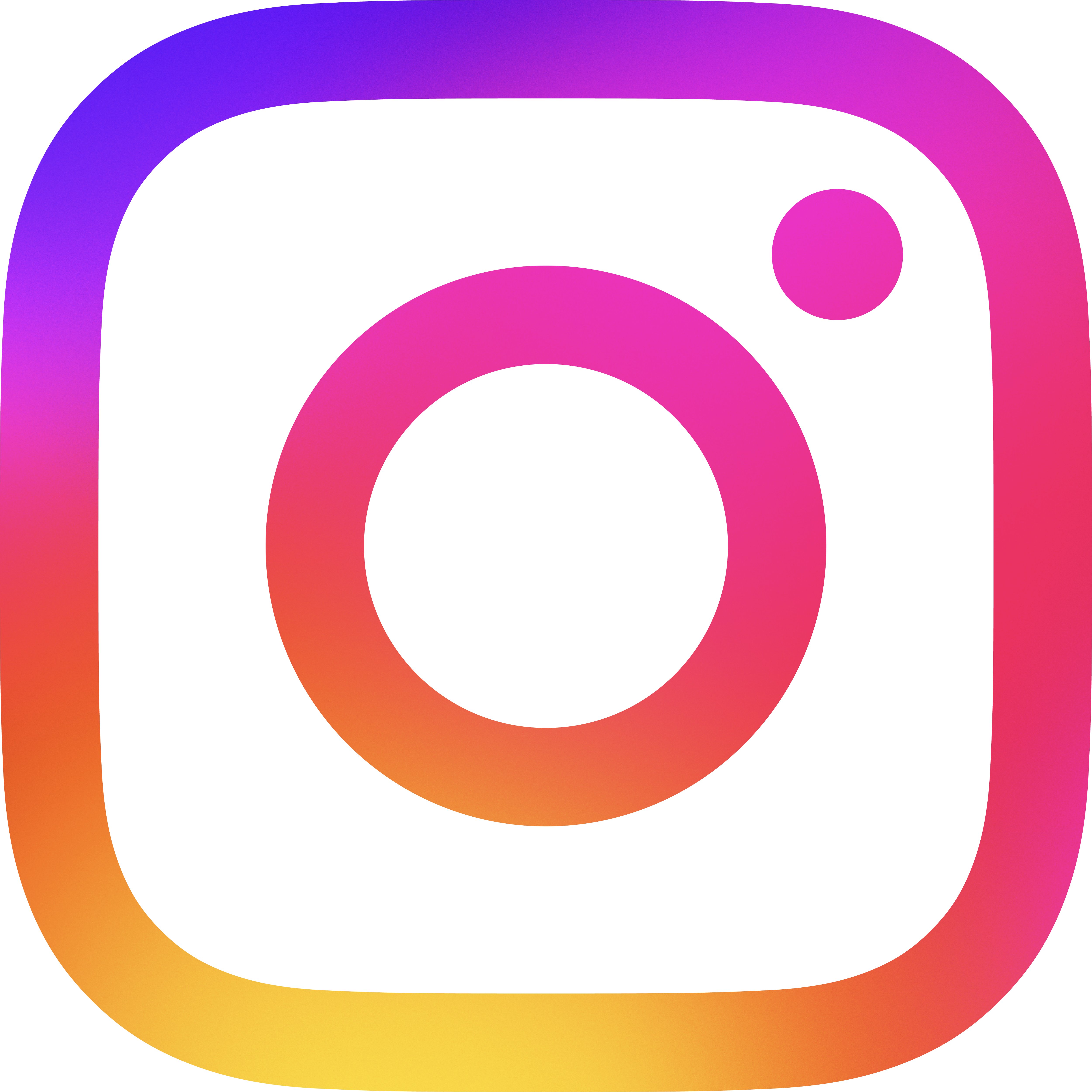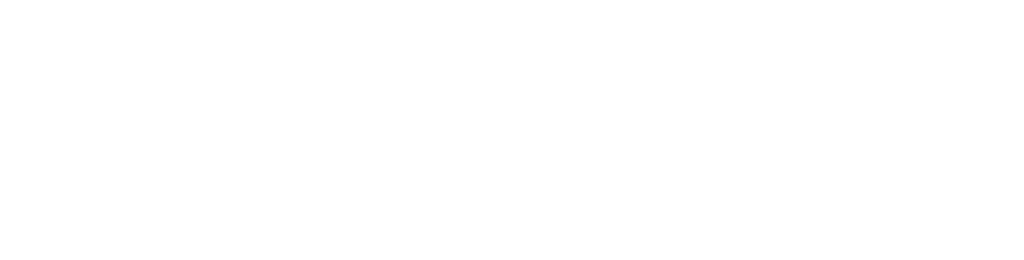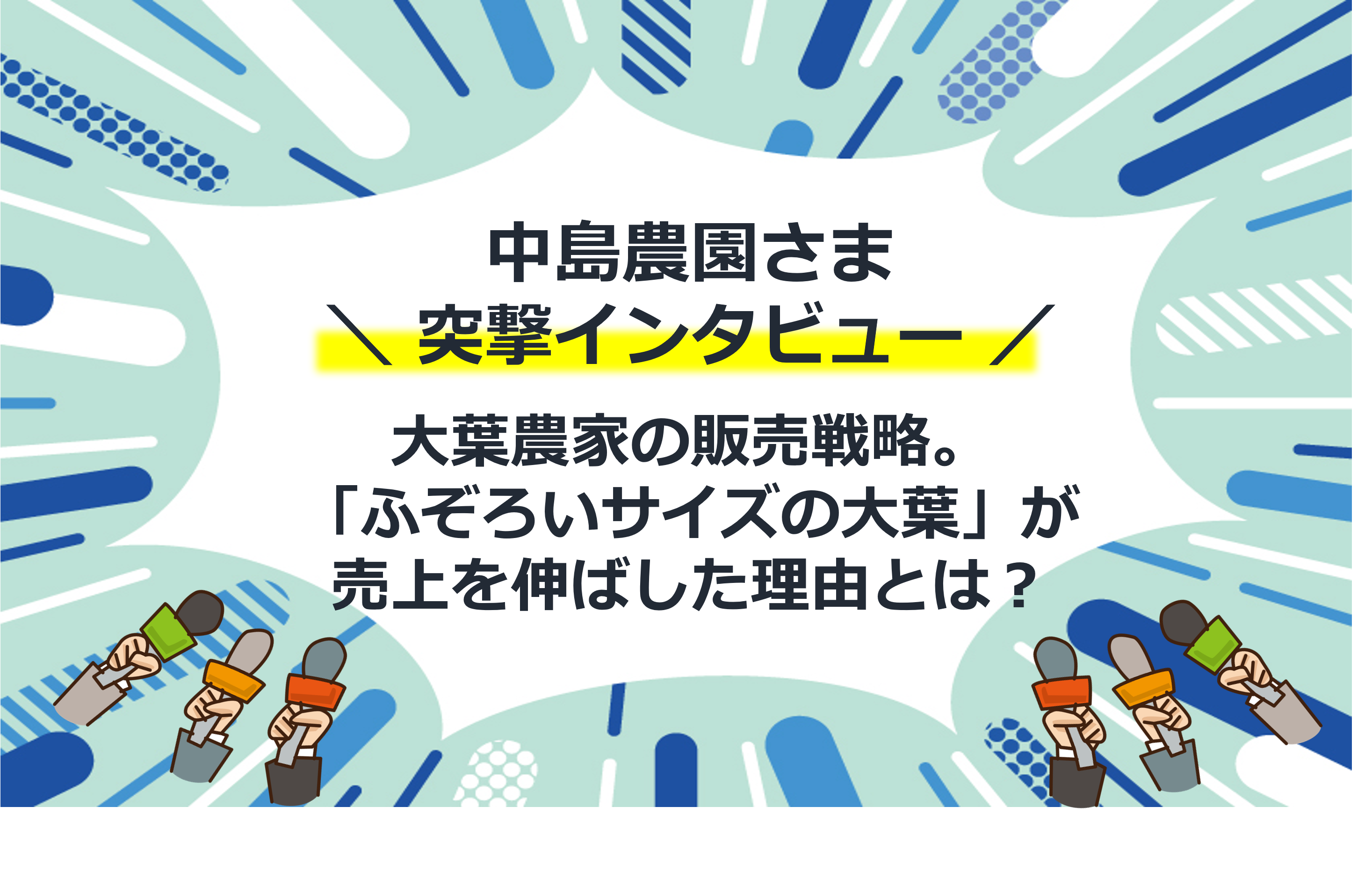
中島農園さま突撃インタビュー
大葉農家の販売戦略。「ふぞろいサイズの大葉」が売上を伸ばした理由とは?
中島農園・代表の中島弘樹さんが実家の大葉農家を事業継承したのは2019年。中島農園の大葉は、香り豊かでありながら、通常の大葉と異なりふぞろいの大きさで袋に詰め、量販店向けに販売されています。しかし、従来とは異なる規格での販路拡大には試行錯誤を重ね、多くの困難に直面したといいます。
さらに、中島農園のユニークな点は、「社長以外は全員外国人スタッフ」という組織体制をとっていること。 多国籍のチームとともに、日本の農業の現場でどのように大葉の栽培を行い、売上拡大に向き合ってきたのでしょうか。そして、ふぞろいの大葉を販売するに至ったきっかけとは?
中島さんに、大葉農家としてのこれまで・これからの経営戦略についてお話を伺いました。
目次[非表示]
Q1.就農のきっかけを教えてください。
A.同志との出会いがマインドや競争心を育んだ。
当時の自分には、選択肢が農家しかなかったというのがきっかけです。本気で農業を志したのは農業大学校での出会いがきっかけでした。料理人志望から農業に転向した栗原農園の栗原さんと同期だったのですが、覚悟を持つ彼に触発され、農業を自分の生業にしようと決意しました。
同世代の農家との出会いが競争心を育み、次第に仕事への向き合い方が変わっていきました。 若手経営者との交流や情報交換から、親の代のコミュニティとは別の形で仕事をいただく機会も増えました。いち「作業員」から、「中島農園の中島さん」として求められている実感が湧き、経験が蓄積されていくことで、自分の農業が形になっていったのです。そうして、「大葉を強みにしよう」と決意し、農業の面白さを心から感じられるようになりました。

Q2.親御さんと農業を共にする中で苦戦したことを教えてください。
A.栽培方法の改善において両親とぶつかり合った。
当時は両親が栽培、私が販売という形で何となく役割は分かれていました。ハウスに居たくなかったんです(笑)
そのうち栽培スキルも身につくだろうと思っていましたが、想像以上に奥深く難しいことを痛感。欠品や品質不良に対応しきれずお客さんに怒られる中で、「このままではいけない」と、栽培に対して専門的な深い知識と経験を持つ必要性を感じました。
そこで、普及センターや専門農家を回り、農薬を減らしつつ病気対策もできる方法を学び、試行錯誤を重ねながら確立。 その過程で、両親の長年の経験の背景を理解し、反発するのではなく、学びとして取り入れる姿勢へと変わっていきました。
一方情報を鵜呑みにせず、見極める力の重要性も実感。 こうした経験を積みながら、より良い大葉作りを目指してきました。
Q3.中島農園で取り扱う大葉の特徴を教えてください。
A.独特の販売方法と、豊かな香り。柔らかさ。苦味の少なさ。
一般的に大葉は飾りものとして活かせるよう、色濃く、大きさの揃った、ハリのあるものが規格として求められます。弊社も、もちろんそういった形態での販売を取っていましたが、私が肥料を与える回数を勝手に減らしてしまい(笑)大小さまざまなサイズの丸まった大葉ができてしまいました。当初、それらは規格外として扱われ、ほとんど価値を見出されていませんでした。
しかし、よく観察すると、柔らかくて香りが高い という特徴があることに気づきました。「これには伸びしろがあるのでは?」と思い、勝手に袋を作って販売を開始。従来のように大葉の大きさを揃える作業が不要になり、調整にかかる工数や人件費の負担が軽減されました。
また、大葉の裏側には香りの成分が含まれていますが、選別や調整作業を減らしたことで、収穫後に触る回数は2回ほどに抑えられ、香りが飛びにくい という利点も生まれました。その結果、「香りが豊かで、柔らかくて苦味が少ない」と評価をいただくように。

とはいえ、すぐに受け入れられたわけではなく、3年は粘りました。 その間に試行錯誤を繰り返しながら、ようやく定量を安定して販売できるようになったのです。
Q4.中島農園の大葉の販売戦略を教えてください。
A.消費者と関わるイベントで、潜在的な顧客を獲得。
中島農園では、「食べる大葉」としての価値を伝え、一般消費者にも広く浸透させること を販売戦略の軸にしています。
先ほどお伝えした通り、通常大葉は「飾り物」として形を揃えて販売されますが、当園では規格外の2L・3Lサイズも含めた「ふぞろいの大葉」をそのまま袋詰めし、ボリューム感を重視。選別の手間を減らすことで、大葉の裏にある香り成分を守り、風味豊かな品質を提供しています。
関東圏での販売機会を活かし、「大葉は飾りではなく、しっかり食べられるもの」という視点をアピール することで、主婦層を中心に「たくさん入っていてお得」と評価され、売上が伸びていきました。
コロナ禍で飲食業界の需要構造も大きく変わっている状況の中、新しい販売戦略を構想し続けることは重要と感じます。「大葉専門農家」としてのこだわりを発信し、大葉のポテンシャルを最大限に引き出す販売戦略を続けていきます。
Q5.外国人労働者の方々との仕事で工夫している点を教えてください。
A.お互いに対等、リスペクトしあえる関係性を作る。
中島農園では多国籍の労働者約20人が働いており、皆仲が良く、居心地の良い職場です。初めは単純作業のみ任せていましたが、代替わりで両親が現場を離れ、私の業務も任せざるを得なくなりました。
「できない」と思っていたことも、要点を絞って依頼することで十分に対応できることが分かりました。 そこで、部門ごとに役割を整理し、ホワイトボードを活用して業務を可視化。結果的に、タブレットでの受注対応や電話対応までこなせるようになりました。
特に、昔からの友人であり右腕的存在のアンさんは、私と共にこの農園を支え、より良い環境を築くために奮闘してくれています。若い頃からの互いの苦労を知っているからこそ、単なる雇用関係ではなく、共に成長し合うビジネスパートナーとしての信頼関係が築けています。
また、ミスを責めるのではなく、どう対処するかを重視しました。 自分でどう修正・対応できるかという力を育てることを意識しています。私自身、細かく口出しはせず、完成度は6割でOKというスタンスです。

こうした環境の中で、スタッフ自身が責任感を持って新しい仲間を紹介し、育成する流れが自然と生まれています。単なる労働力の補充ではなく、「この職場で一緒に働きたい」と思える関係が築かれているからこそ、紹介の輪が広がるのです。また、互いに支え合う文化が根付いているため、手を抜いたり怠けたりすることが恥ずかしいと感じる空気があり、自然と仕事に真剣に向き合う姿勢が生まれています。
外国人スタッフとも対等な関係を築きながら、一緒に農園を成長させていけることこそが、中島農園の最大の強み。これからも、働く人たちが誇りを持ち、楽しく働ける環境を守り続けていきます。
Q6.クロスエイジはどんな存在ですか?
A.現実的なアドバイスをくれる存在。
元々計算で農園の経営をやってきたわけではなかった私としては、藤野さんは具体的な数字を交えながらロジカルなアドバイスをくれるありがたい存在です。
Q7.今後のビジョンを教えてください。
A.「規模感」が持つ影響力を活かす。
今年はハウスを増やし、規模拡大を図っています。中島農園では多くの外国人労働者が働いており、彼らが安心して働ける環境を整え、「外国人労働者は安く雇える」という概念を覆したいと考えています。
私自身、現在37歳で、まだ農家の中では若手です。しかし、農園の規模が大きくなるにつれ、周囲の関連会社との関係構築がしやすくなり、実績を積むことで世間からの評価を高めるチャンスが広がります。そのためにも、売上を上げ、農家としての経営基盤を強化していくことが重要だと考えています。
また、何事も「とりあえずやってみる」中でトライ&エラーを繰り返し、方向性が見えてくるものだと思います。入口のハードルを上げすぎず、でも「これが全てではない」「今だけ上手くいっているだけかもしれない」 と考え、客観的に自社の立ち位置を見極めるようにしています。
最終的には、地域の産地を守るための取り組み にも力を入れたいと考えています。農業の未来を支えるために、事業を成長させながら持続可能な形で地域の農業を守る。そのための土台を築いている最中です。
大葉に一点集中しながらも、独自のスタイルで売上を伸ばしてきた中島農園。
ふぞろいの大葉の販売を軌道に乗せられたのは、中島さんの品質へのこだわりと、消費者の声を丁寧に聞く姿勢があったからこそ。固定観念にとらわれず、「どうすればもっと良くなるか」を常に考え、挑戦を続けてきました。また、組織運営においても、働く人へのリスペクトを大切にし、より良い環境を作るための試行錯誤を惜しまない姿勢が印象的でした。
相手を信頼し裁量を与えることで、スタッフが自ら考え、動ける職場を築いています。真っ直ぐで柔軟、そして学び続けることを忘れない中島さんの姿勢に、農家としての強さを感じました。
中島さん、貴重なお話をありがとうございました。
(執筆:柴萌子/編集:ひのりほ)