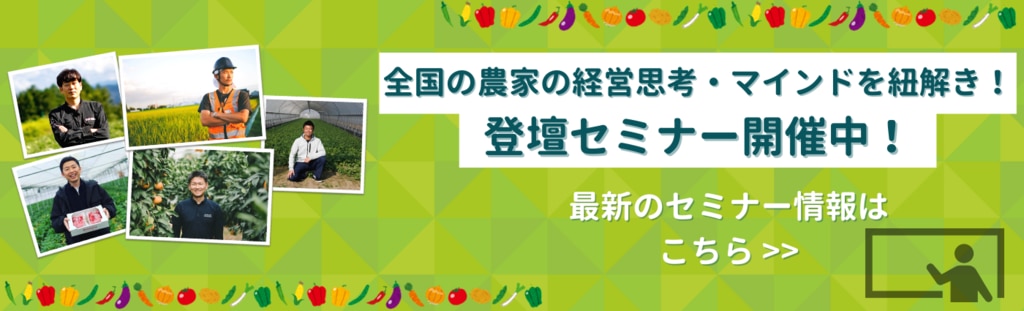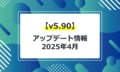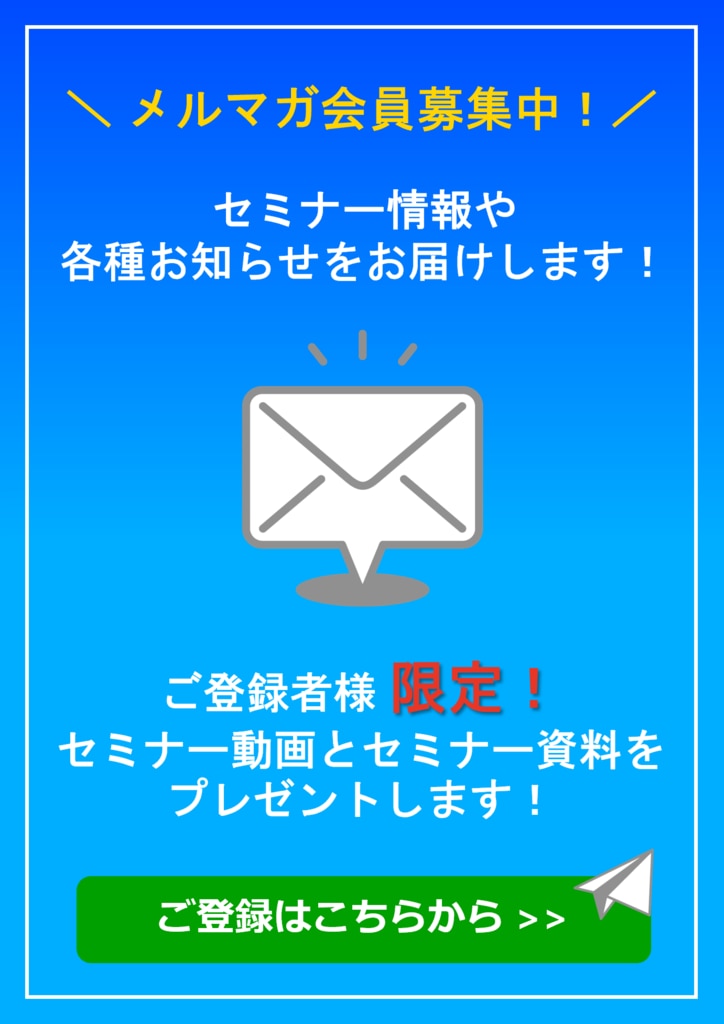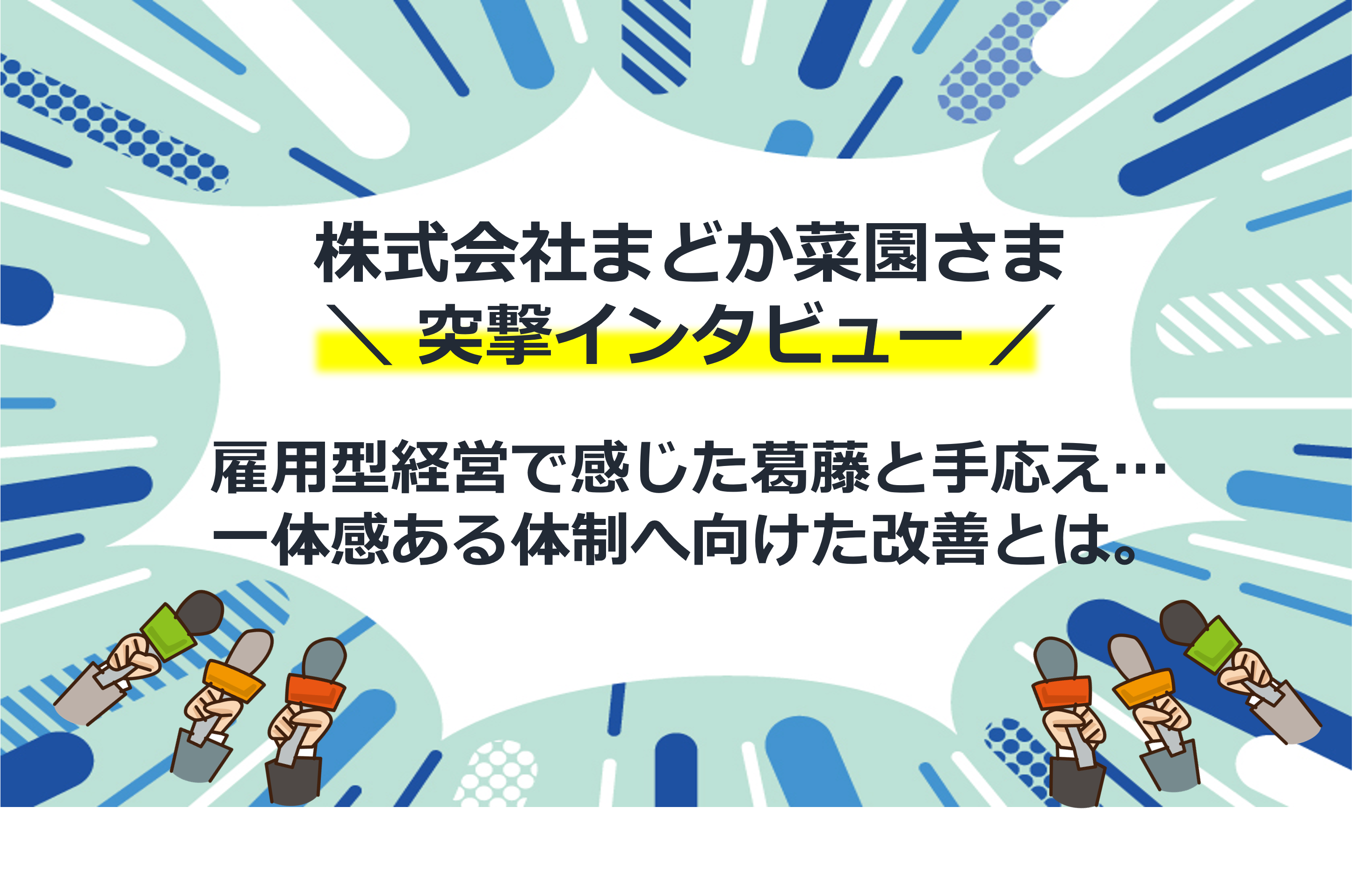
株式会社まどか菜園さま突撃インタビュー
雇用型経営で感じた葛藤と手応え…
一体感ある体制へ向けた改善とは。
ジャンボなめこ栽培の先駆者的な存在で知られている有限会社鈴木農園さまの新たな法人として、2013年に設立された株式会社まどか菜園さま。
枝豆・人参・カブを中心に「郡山ブランド野菜」の栽培を展開しています。
鈴木農園の専務兼、まどか菜園の代表の鈴木清美さんは、「ヒトとのご縁を大切に、地域農業の活性化を」という思いをもって循環型農業に取り組まれています。
今回は、鈴木さんに組織育成までの道のり・取り組み、行動変化についてお話を伺いました。
目次[非表示]
Q1.就農のきっかけを教えてください。
A.父の栽培した「ジャンボなめこ」を食べて衝撃を受けた。
元々は農業に携わるつもりはありませんでした。高校時代に薬学部を目指していた時期もありましたが、将来を考えたときに、実家だけでなく自分の身近には当たり前に農業があることを感じ、“食”に関わる仕事がしたいと思って、農学部に方向転換しました。
農学部を卒業後、コンサル事業を行っている一般企業に就職しましたが、体を壊してしまい…。
今後の仕事について考えているときに、父が代表を務める鈴木農園の仕事を手伝う機会があって、東京・六本木のレストランで開催された、生産者とシェフ、消費者が参加するトークライブイベントに登壇したことがきっかけでした。
それまでは実家で作っているものをわざわざ食べようと思わず、食べたことがなかったんです(笑)僕自身、自社商品を口にしたのはその時がほぼ初めてで。
美味しさに衝撃を受け、感動したのはもちろんですが、そこにいらっしゃったお客さんの反応なども伺う中で、父が築いてきた農業経営を客観視でき、こんなに美味しいものが作れる農業って面白そう!美味しいものを広めたい!と思いから2012年に就農しました。

Q2.法人それぞれの構成・役割について教えてください。
A.循環型農業で雇用・品質・供給の安定。
鈴木農園は父が代表を務め、ジャンボなめこの生産が中心で、約50名の方が働いてくれています。
まどか菜園は僕が代表を務め、枝豆・人参・カブを中心に「郡山ブランド野菜」の生産・販売、ジャンボなめこの販売を行っていて、社員10名・パートさん10名の合計20名の方が働いてくれています。
なめこ栽培後に発生する、廃菌床を堆肥化することで、化学肥料の使用量を抑え、循環型農業によるSDG’sに取り組んでいます。化学肥料の使用量を抑えていることが取引先に対してPRポイントにもなり、有機質肥料を中心にすることで土壌環境変化を緩やかにし、根痛みなどを軽減することで収量安定にもつながっています。
なめこは予冷管理が必要で冷蔵設備が充実していることで、なめこだけではなく枝豆や人参も品質の劣化軽減、悪天候などに左右されにくい供給体制が可能になっています。なめこや野菜を年間通して栽培することで一定の仕事量があり、雇用の安定にもつながっています。
循環型農業でグループで連携できるからこそ実現できる”安定”が強みだと思っています。
Q3.品目選定において意識したことはありますか?
A.味での差別化と通年雇用。
品目選定のポイントは2つです。1つ目は、郡山が野菜の産地でないからこそ、食味や機能性の高い産地化に適さない品種を選定し、産地と味の差別化を図れるか。2つ目は、通年雇用ができるかどうかです。現場スタッフが1年間農業だけで食べていけるか、ちゃんと通年仕事がある状態にできるかどうかも考えて選定しました。

Q4.経営においてのターニングポイントを教えてください。
A.8期目に社内体制を大幅に変更。
去年の秋ごろから僕が現場に出るのは1~2割になりました。意図的にそうしている部分もありますが、現場からそうさせられている部分もあります。現場に出る楽しみがないので寂しいですが、トラブルが発生しても僕の前で終わっている状況になってきて、すごく良いことだなと感じています。1番下の弟が戻ってきて、弟を中心に男性と女性のリーダーも管理業務を回せるようになってきて、リーダー職が機能し始めていると思います。去年までは社員も作業者の意識が強くて、社員は作業者ではなく、管理業務に重きを置いて行動してほしいと求めるようになって、今年に入ってから行動に変化が見られるようになってきました。
赤字がひどく大変な時期もありました。このままだと赤字を拡大させるだけの会社になってしまうと思ったのが8期目で、年末に社員全員を集めてミーティングをしました。それまではスタッフに会社のお金の話しはしたことがなかったんですが、人件費ばかりがかかって、面積が増えても利益が増えていない状態だから、働き方を変えないといけないと、腹を割って話し合いました。鈴木農園時代から長年勤めてくださった方も居ましたし、「変化」に対して寛容さは人それぞれ、スムーズに話は進みませんでした。ただ全員と話していく中で、今変化を起こさないと会社が潰れると思ったので、社員とマインドをすり合わせました。社員から「●●さんをリーダーに!」と意見を出してくれて、社内体制の変更を行ったことで少しずつ社員のマインドにも変化があり、今につながっていると思っています。
Q5.クロスエイジはどんな存在ですか?
A.定点的に自分を見直させてくれる存在。
月次で数字を振り返るのとは別で、クロスエイジさんと話すときは月単位で自分の行動を振り返ることができています。次にどう行動すべきなのか考えたり、定点的に自分を見直すことができています。
また、エリアを越えた農家さんと出会うきっかけをもらえるのもありがたいです。エリアを越えているからこそ話しやすいこともあったりするので、貴重な情報交換の場にもなっているので、助かっています。
Q6.今後のビジョンを教えてください。
A.現場スタッフと一緒に体制と作り上げたい。
まずは枝豆だけで売上2億円を目指しています。ただ、今後さらに上のフェーズを目指すには管理者の育成・昇給制度など、組織体制の構築が必要だと強く感じています。
もちろん現場スタッフの協力のおかげもありますが、今の経営の規模は自分で考えられる範疇のアッパーに近づいていると思っていて、今後さらに販路拡大や農地を広げることを考えたときに、現場は現場で考えて動いてもらわないと難しいと思っています。
今年のテーマとして、現場スタッフには「スタッフが現場を回せる体制を一緒に作りましょう」と伝えています。上のフェーズを目指すためには、僕は現場ではなく、現場のことは現場で管理できるように、毎日の作業を”ただの作業”としてではなく、”作業の本質を理解”して動いてほしいと伝えています。うるさいくらいに「なんで?」と問いかけて、現場スタッフに作業の本質を理解してもらって、僕がいなくても現場は現場が回せる体制を一緒に作り上げたいと思っています。

僕の個人的な希望は50歳くらいで退職したいなとも思っていますが(笑)僕自身も経営者としてスキルアップを続けないと僕が会社にいることが負担になるときが来てしまうと思うので、そうならないためにも”やるべきことをやるべき人がやる”体制を構築して、さらに上のフェーズを目指したいと思っています。
鈴木さん、貴重なお話をありがとうございました。