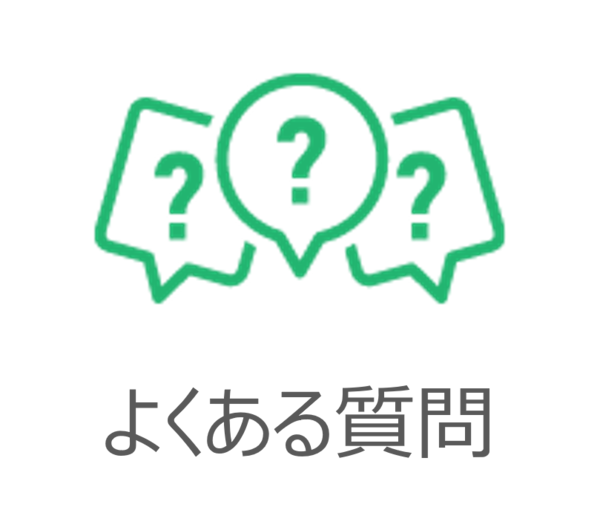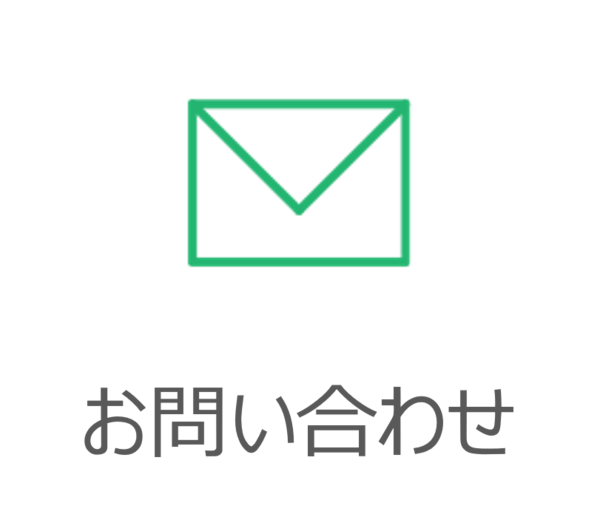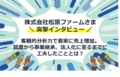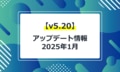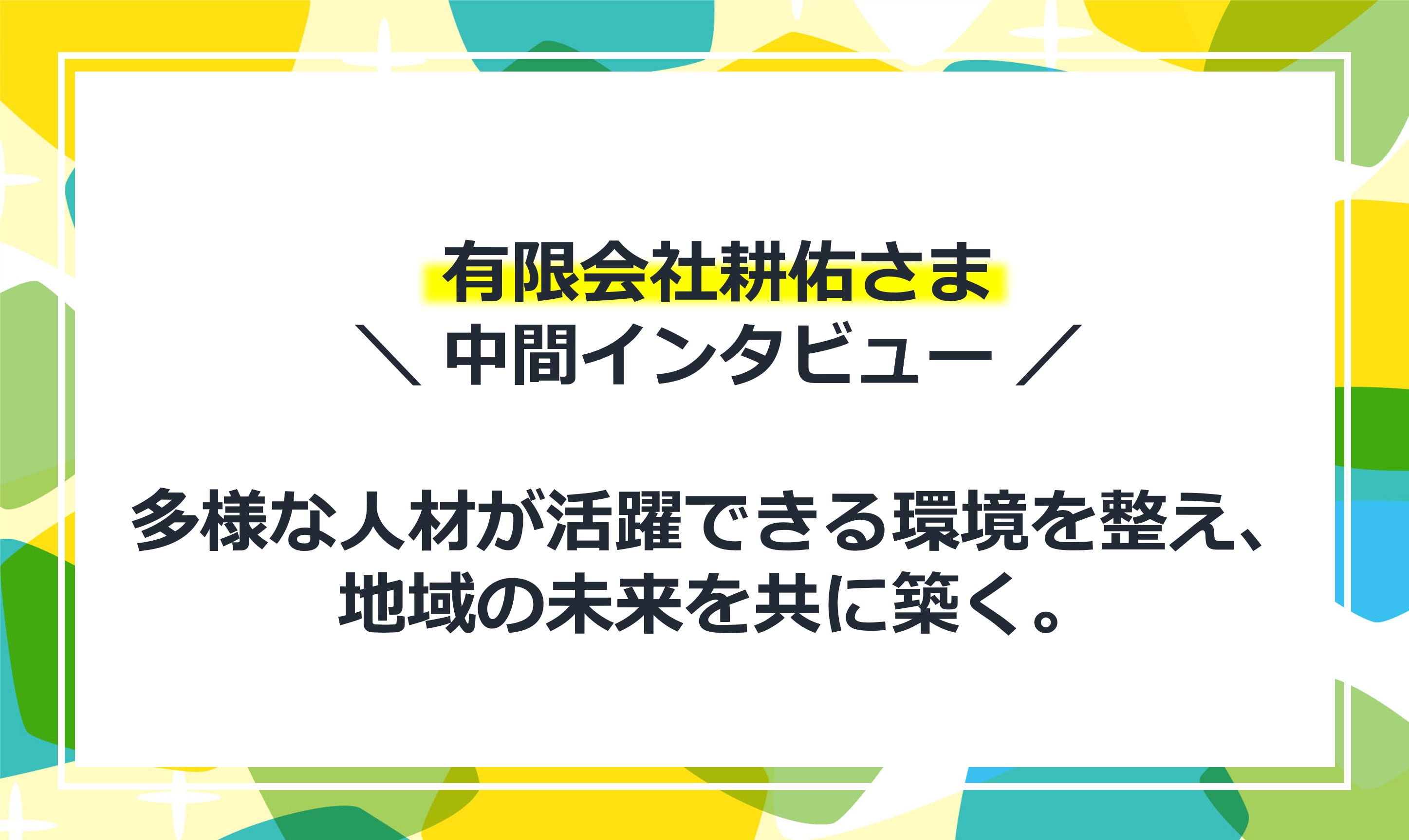
有限会社耕佑さま中間インタビュー
多様な人材が活躍できる環境を整え、地域の未来を共に築く。
株式会社クロスエイジ(以下、クロスエイジ)は、「大規模農業経営の安定した人材確保と経営」「障がい者の農業現場での活躍」ができる地域や社会を目指すべく、休眠預金活用事業における資金分配団体として、農福連携推進のために活動する6実行団体の支援を行っています。
今回は本プロジェクトの実行団体である、宮城県でサンチュ、サラダ菜、みつばなどを水耕栽培している有限会社耕佑(以下、耕佑)の代表取締役・伊藤 秀太さまに休眠預金活用事業に申請したきっかけや事業発案への想いをお伺いしました。

耕佑さまの事業について教えてください。
耕佑は30年ほど前に栗原市一迫南沢地区で4戸の稲作農家の共同作業から始まった会社です。
地域の営農を維持し、地域で雇用を生むために立ち上げた会社で、1年間を通して仕事をしていくために、当時宮城県では珍しかった葉物野菜の水耕栽培にチャレンジし今に至ります。2021年に私が継承し、従業員は約30人で、売り上げ規模は約2億円です。ハウスは全部で10棟あり、栗駒山の伏流水を使って、サンチュ、サラダ菜、みつば、ケールなどを栽培しています。メインで栽培しているサンチュは、東北や首都圏のスーパー、飲食店で広く販売されています。2023年から栗原市および近郊の舞茸農家から事業継承して舞茸栽培も始めました。地域で雇用を生むために農業を続けている会社です。

休眠預金活用事業に申請したきっかけを教えてください。
2024年7月にNPO法人BALLOONを設立し、A型・B型の就労継続支援多機能型事業所の運営をスタートしました。耕佑への施設外就労をメインにサンチュの収穫などの農作業を利用者の方々に提供しています。
「Think local. think normal.」を理念に、「地方の強みで課題を解決する」「多彩な個性が調和する日常を築く」ことを行動指針として、農業を中心とした事業で地域の障がい者と健常者が共に働く環境や持続可能な社会作りを目指しています。
休眠預金活用事業に申請し、NPO法人BALLOONを設立したきっかけは主に3つあります。
1.農福連携による地域課題へのアプローチ
まず第1には、地域の深刻な人口減少と、それに伴う人材不足への危機感がありました。地域経済や基盤である農業においても、従事者の減少が進み、人手不足が深刻化しています。
耕佑は、設立以来、役員とパートさん達でやってきた会社ですが、年々パートさんたちが集まりづらくなってきており人手不足に直面しています。これからも地域で農業を続けていくには、地域住民や健常者だけでなく、特定技能の外国人や障がい者雇用も行い多様な人材リソースを活用することが不可欠だと考えています。
耕佑でもこれまで障がい者の雇用や就労支援事業所からの施設外就労の受け入れを行ってきましたが、福祉法人を新たに立ち上げることで、障がい者の方の働く場づくりや農福連携からの地域課題へのアプローチがしやすくなると考え、設立に至りました。
2.異業種からの参入だからこそできる農福連携の仕組みづくり
耕佑で障がい者の雇用や就労支援事業所との連携をする中で障がい者雇用の可能性を感じる一方で、福祉側と農業側の目指す方向性の違いや課題にギャップがあることを実感してきました。
このギャップを埋めることで、双方がより良い形で連携できる仕組みを作りたいという思いがあり、また社内に福祉部門を作るよりも別法人として立ち上げ良い関係を築いた方が現場の納得感が高いと考え、福祉法人を立ち上げようと決めました。
NPO法人BALLOONは農業、料理人、食品加工の専門家など農と食に携わる経営者が理事になっています。各々のメンバーが得意とする分野で事業行うことで、障がい者の方々の多様な働く場づくりや、これまでにない農福連携の仕組みをつくることができると考えています。
3.柔軟な支援と地域に根ざした働く場の提供
耕佑で働く障がい者の中には、親御さんの送迎がなければ通勤が難しい方もいます。親御さんがいなくなってしまったら通えなくなってしまう。そうなったときに彼らが働き続けられるようにしたいけれど、一般的な企業では、従業員のプライベートな事情に柔軟に対応することが難しいのが実情です。就労支援事業所であれば、送迎のサポートをはじめ、個々の状況に応じた柔軟な支援が可能です。NPO法人BALLOONでは、将来的にグループホームの運営も行っていきたいと考えており、障がい者の方々が地域に住み、働くことができる環境を整えることで、自分らしく輝き、さらに地域や社会全体にも良い影響を与える事業を目指しています。
現在の休眠預金事業の状況を教えてください。
NPO法人BALLOONの設立にあたっては、市内のA型事業所が閉鎖することになり、その利用者の方々の働く場が失われる状況になったため、予定よりも急いで事業所を開設し受け入れを開始することになりました。結果的には、順調に事業を開始することができたものの、事業所となる施設の施工とサービス管理責任者の採用には苦労しました。
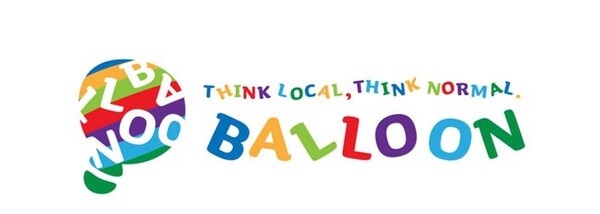
事業所については、福祉施設として消防法や福祉条例の基準に適合した施設とするために多くの時間と費用がかかりました。施工には約1,000万円が必要で、施設の準備には半年以上前から取り組んでいたものの、最終段階では多忙を極めました。
サービス管理責任者の採用については、資格が必要なポジションであるため人材の確保が難しかったのですが、事業所の立ち上げから一緒に取り組んでくれる経験豊富な方に来ていただけたことは幸運でした。私たちに専門知識が十分でない分、サービス管理責任者の方の存在は非常に重要です。
実際の現場は、立ち上げにあたって参考にした事例や書籍等の情報と異なる点も多々あり、現場で試行錯誤しながら学んでいることも数多くあります。これからも現場の実情に応じて柔軟に対応し、着実に運営を進めていく予定です。
今後の休眠預金事業の予定を教えてください。
NPO法人BALLOONは始まったばかりの福祉法人であり、現在の最優先事項は、耕佑での施設外就労のスタイルを確立し、利用者の方々が安心して働ける環境を整えることです。また、当法人の強みであるA・B型の多機能型就労支援事業所としての特性を活かし、利用者の状況や目標に応じた就労のステップをサポートしたいと考えています。
例えばB型からスタートした方が成長し、A型へと移行して工賃が上がることで、努力が成功体験に結びつく仕組みを作りたいと考えています。成長と報酬の実感を持ってもらえる環境を提供し、自立を支援していきたいと思っています。

将来的には地域の他の農業法人や飲食店での施設外就労も視野に入れ、地域社会に貢献できる場を広げていきたいと考えています。また、NPO法人BALLOONの理事のメンバーが各々得意とする分野での事業を展開し、将来的には福祉レストランを開業することも目指しています。
耕佑の水耕栽培収穫作業を軸に段階的に食品加工・福祉レストランなど多様な働き方で活躍できる場を作り、共に成長していける環境を整えていきたいと考えています。農福連携は単なる雇用の枠組みを超えて、地域社会全体の活力となりうる可能性を秘めています。今後も一歩ずつ進んでいきたいと考えております。
(執筆:柴萌子/編集:ひのりほ)